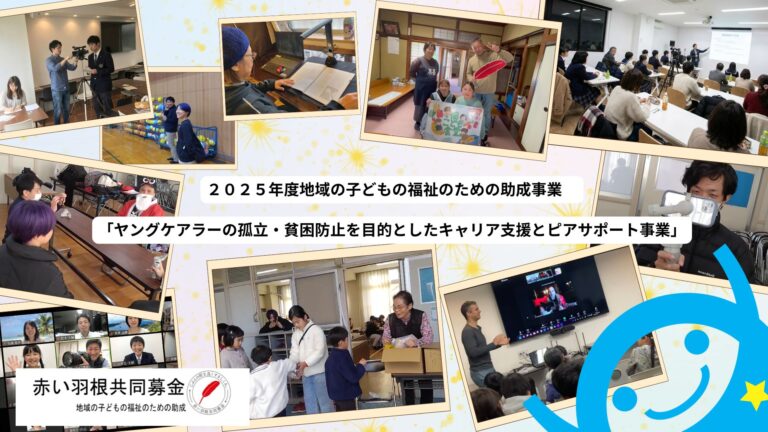私たちわかこくの濱田理事は、いつの頃からか根っからのノマディアン(遊牧民)型 👨💻 ワークスタイル 👨💻 を実践しています。
理事は、現地で生活しながらわかこくで貢献できるICT活用型開発の視察検証をしています。
アフリカからご報告いただきました 🤳

2019年12月のはじめ、アフリカのウガンダに着任し、首都カンパラで国際NGOの事業開始に向けた各種準備を進めています。
ウガンダは、「アフリカの真珠」と謳われるほどの美しい国で、首都カンパラでも十分すぎるほどの自然を満喫できます。

上の写真は、滞在先ホテル(三階)から撮影しました。
一面にジャングルのような緑が広がっています。山間部には 🦍 ゴリラ 🦍 も生息しています。
約三カ月間の緊急援助を行うプロジェクトの準備をしています。
ウガンダ北部のユンベにある同国最大規模の南スーダン難民居住区のBidi Bidiで、南スーダン難民のトラウマや心的外傷後ストレス障害などを軽減するために、日本人の専門家(精神科医)や地元NGOの専門家(ソーシャルワーカー)などを招いて、心理社会ケアを実施します。 日本でも一定数の人たちがトラウマや心的外傷後ストレス障害を抱えています。南スーダン難民のトラウマというのは凄まじく、同国の内戦で両親や兄弟、親戚や友人・知人などが目の前で反政府軍やゲリラに射殺されたり、暴行されたりといったレベルです。

そういった南スーダン難民が現在でも、ウガンダ国内において20万人以上生活しています。20万人以上という数字は、Bidi Bidi難民居住区で把握されている数字なので、実際はもっと多いはずです。
紛争や難民問題と聞くと、日本人の感覚からすると、遠い世界のことに思えます。日本は島国で国境がなく、また非常に平和の国だから仕方ないことかも知れません。
先月まで、アフリカの最貧国と言われるマラウイで緊急援助(食糧援助)を実施していた時に、栄養失調の貧しい子供たちを沢山見ました。公的機関の統計によると、日本での食品ロスの総量(年間)は、国際機関や各国政府による途上国への食糧援助量(年間)をはるかに上回っています。マラウイから日本に一時帰国した時に、コンビニなどで廃棄される食品を見るたびに、栄養失調のマラウイの子供たちが思い出されました。

お姉ちゃんが食べているのはサトウキビです。
昔、日本でもこういう光景があったのではないでしょうか……
今一度、自分の足元を見直す良い機会が、国際協力には沢山あります。
もし興味がありましたら、本屋で国際協力の本を一冊立ち読みしてください。
日本国内の社会問題と、こんな遠くの途上国の支援活動とはまったく関係が無いと思われるかもしれません。
しかし両方を現場で仕事をした人なら、そこに骨太の共通性を見出しているはずです。
詰まるところ、私たちわかこくが国内で実施している多文化共生活動と途上国でのコミュニティベースの活動とは、非常に似通った所があります。

「グローカル」という言葉が良い例です。
国内の福祉問題でも、公共サービスや専門家の支援にはコストがかかって持続性が無かったり、支援ー被支援の関係が目に見えてその効果に限界があります。
そのため、多くの場合は市民の助け合いや自助グループ、市民活動など互助の精神で持続的な支援を行います。
途上国でも同じです。貧困で心身が疲弊した人々に、寄り添いながら持続的な発展を実現するためには、コミュニティの形成や助け合いを実現する参加型の仕掛けが必要になります。

後ろに見える木は、かの有名なアフリカのバオバブの木です。
国内外の若者支援には、何かしらお互い琴線に触れるところがあると思います。
そうなればしめたもので、次のステップやアクションが見えてくるものです。

日本の社会福祉は、生存の危機に立つ人々への福祉と、幸福の意味や価値観に関わる福祉に二極化しています。
こういった途上国に来ると、自分が置かれている豊かな環境のことを相対化できて、何か得られるものがあるかもしれません。

家は木と草でできています。
日本国内の問題は、もちろん深刻度を増しています。
「今の自分は不幸だ」、とか、「過去につらい経験があって」と自分の殻に閉じこもってしまいそうなとき
思いつめた気持ちになる前に
一度、自分が知らない世界や生活、文化や価値観をみてみてはどうでしょうか。

自分とはまったく違う環境と生活を送っている人の笑顔や悩みに触れることで、今の自分を初めて知ることができるかもしれません。
あ・・・とってもいい記事になりました! 😝🥳
濱田理事、ありがとうございました!