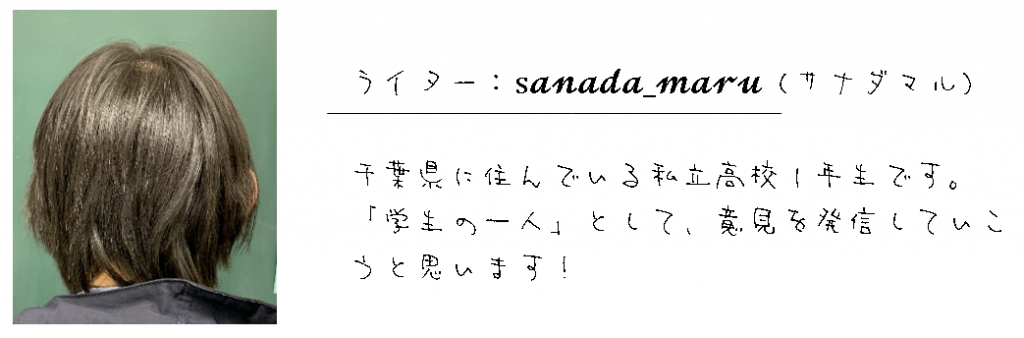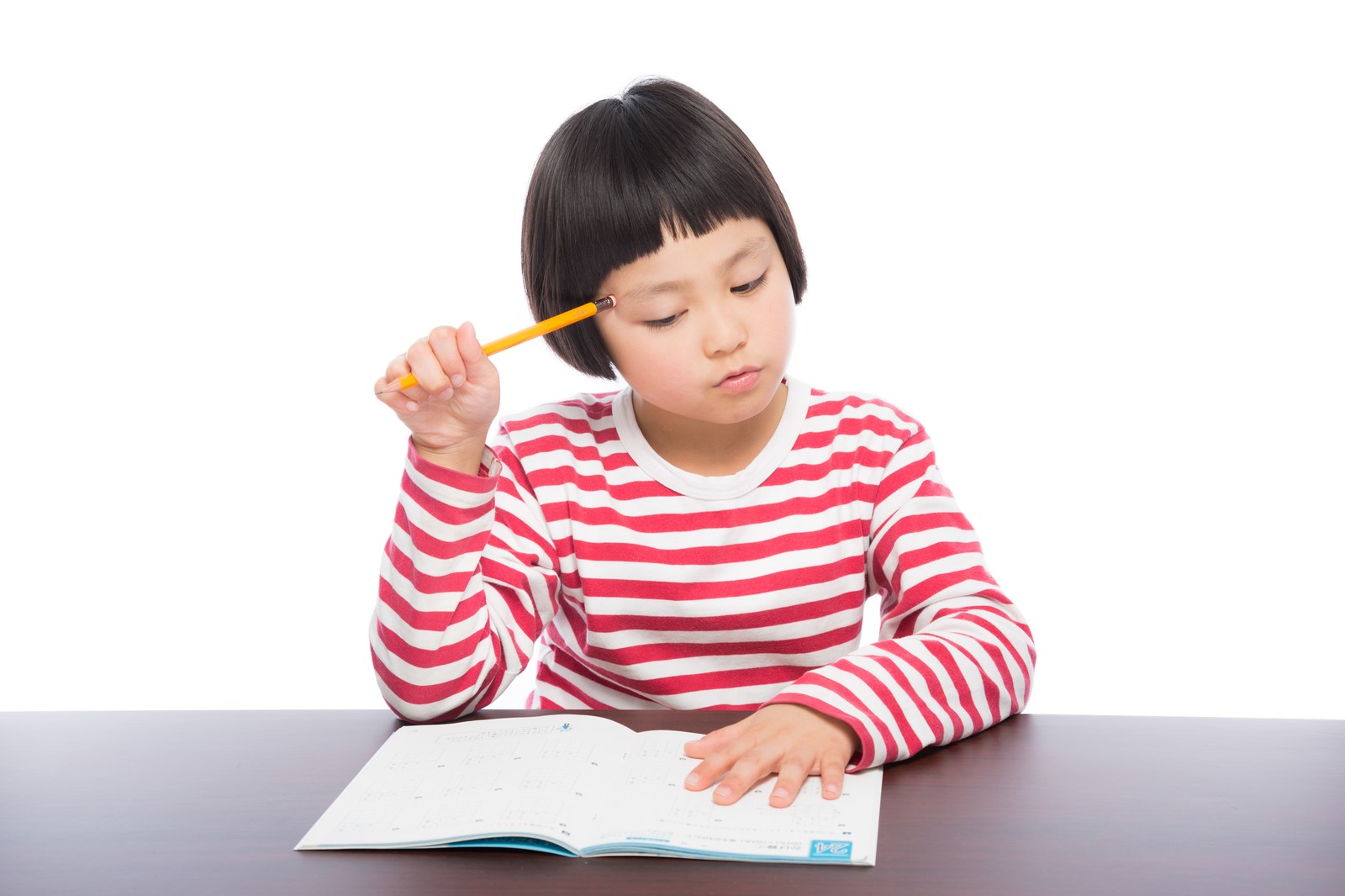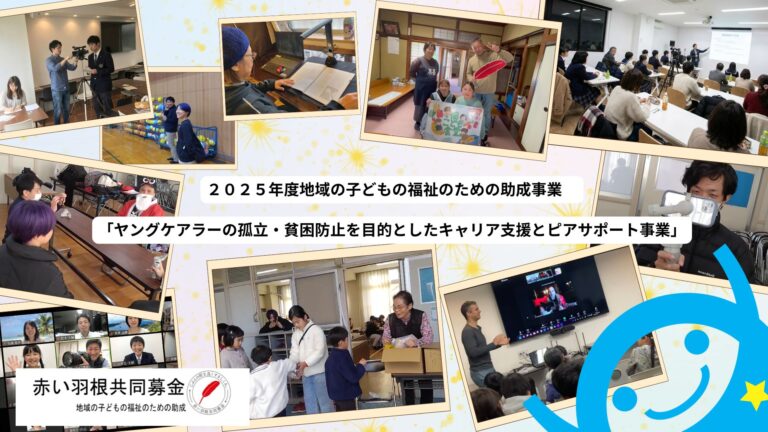高校1年のsanada maruです。
前回の記事で「どうすれば勉強が楽しくなるのか」ということを最後に書かせていただきました。
今回は、その具体的な工夫についての話です。
そもそも、勉強といわれたって…という人は、多いかと思います。
私もよくわかります。
そもそも何の役に立っているのかわからない。
何をしているのかわからない。
誰のためにやっているのかわからない。
勉強に対してのやる気が起きない大きな理由はそこにあるでしょう。
勉強ができない。成績が上がらないだから面白くない、つまらない。そこから勉強を嫌いになってしまうように思います。
それでは、今回は少しでもそういったマイナスの気持ちが減るようにと、勉強を好きなる工夫をお伝えしたいとおもいます。
全ての基本「形(かたち)」

まずは形から入りましょう
形は、非常に重要なことだと思います。
例えば、言語(日本語や英語など)を習得する際、人間はどうやって習得するのでしょうか。
そもそも生まれたばかりの人間には、言語を話す能力はありません。
成長過程において、特に2歳前後のころに自然と発声ができるようになります。
その際、「あ」や「う」などの言葉を発します。
その発話する音声に対して、言葉を意味あるものにしてくれるのは、あくまでも周りにいるほかの人間(大人など)です。
言葉に意味を持たせる、あるいは文字、声、音に意味を持たせると言った方がいいかもしれません。
同様に、勉強を好きになるには、それに対する意味を勉強そのものの外<ソト>から与えていく必要があります。
わかりやすく、私の場合をご紹介します。
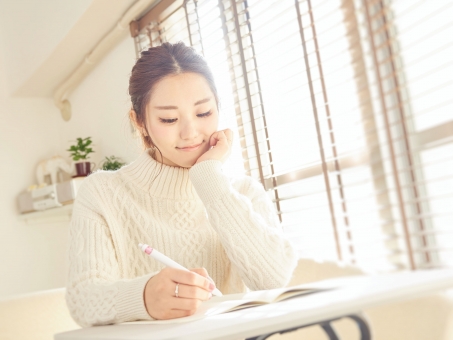
私は勉強を始める前に、環境を整えます。
まず、自分の高さ(座っている方が好ましいです)にあう机の高さと椅子の高さをセット。
それから、机の上を平らにします(整理してもよし、本同士をくっつけてフラットにするもよし)。
次に使用するのは「ルーズリーフ」。
これは自分にとって勉強するにはもってこいです。
どのメーカーのどういったルーズリーフ(たとえば、罫線の有無、方眼紙タイプかどうかなど)が最適なのかは個人の差があると思います。
(いつかほかの文房具類と合わせて紹介できたらいいなと思っています)
私は勉強の内容の意味をいきなり考える、というよりも、ルーズリーフという道具という形が自分に与えるモチベーションを大事だと考えています。
たとえば、ルーズリーフの良いところは、あとから差し替えや順番の入れ替えができること、また不要になったページや追加のノートをいつでも増やせることです。
つまり、ノート整理の失敗のリスクが減るということです。
たしかに、ルーズリーフはノートに比べると、紙がまとまっていない分、紛失の可能性が上がります。しかし、教科書通りの順番で問題を解かない人や、授業以外の機会での勉強時間をもつタイプの人にはおすすめのツールです。
たとえば、ばらばらの場所や時間で作成したメモやノートでも、最終的に、順番を差し替えることで教科書通りの順番を構成することが可能です。
さらに、ルーズリーフは持ち運びの量を調整できますし、ぎゃくにノート以上のページ数をもたせてまとめあげることもできます。
そして、枚数が少しづつ増えていくたびに、それだけ自分が勉強した量が可視化されます。
目で見て自分の努力がわかるため、感覚的に達成感がわかるようになります。
達成感があれば、次もまた勉強しようという気になれる。
それが、私の場合、限りなく止まらない次の勉強の意欲をつくりだしてくれます
このように形からから入ることで、勉強することに「達成感を得る」という意味を自ら与えることができました。
勉強はあえて休日にやるべし!
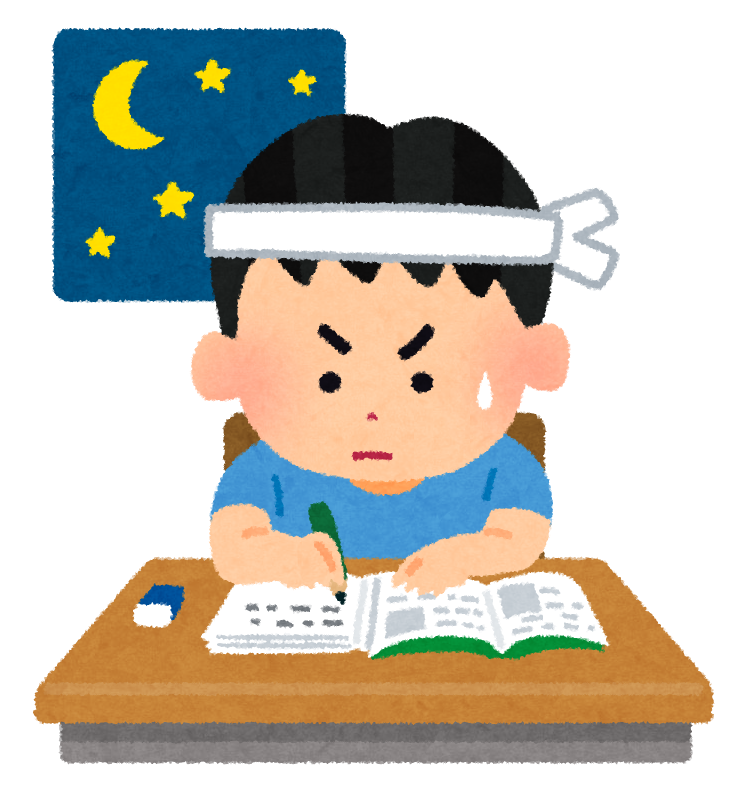
次に重要なことは、勉強する量を増やす、ということです。
中高生になると、勉強の日々に追われます。
たとえどんな学校にいても、生徒である以上、勉強から逃れることはできません。
勉強しなければ、落ちこぼれていってしまいます…。
では、どうすればやる気を出すことができるでしょうか。
私の場合、その方法は、休みの日に勉強をすることでした。
休みの日になんて…と思う人がいるでしょう。
もちろん、休日は思いっきりゲームをしたり、外出して友達と遊んだりとリラックスできるとても重要な日です。
でも、休日に、特に予定が入っていなければ、ダラダラして過ごすのはもったいない。
たとえば、お金を使い切れと言われれば喜んで私たちが使い切ろうしますよね。
同じように、時間もしっかり、使い切りたいと思ってみるべきだと思います。
周りが勉強していない間、自分が勉強をしている。
ほかの人より余分に多く成長できる時間とチャンスを得られる!
そう考えると何だか、ぞくぞくしてきませんか?
私はしてきます……
自分が使った時間が有意義であった、と感じられることから、自尊心というものも高めることができると思います。
逆に、休みの日に遊び過ぎていたり、「勉強も何もしてこなかった……」と振り返って不安になるような遊ぶだけの時間を過ごすと、自分に対する自信もなくなっていきます。
逆に勉強にしっかり時間を費やした!と達成感を感じることなしに、成績を上げたり勉強を楽しく取り組みことなんでできないと思います。
さて、大きくこの二つさえ、守れてしまえば、自然と勉強の意味を持てるようになるはず!
勉強に取り組むことが楽しくなるような、形・環境を整えていく、その工夫さえもワクワクしてくるはずです。
そして、成長している自分を意識するように工夫することは、気持ちの面でも健康的に過ごす人間の一つの生き方として、大事なことだと思います。

まとめ
今回は、「勉強をどうやって好きになるか」、というちょっと難しい問いに私なりに回答してみました。
まとめますと……
(1)自分が勉強に意味を見出せるように、勉強道具や環境などの「形」を大事にして、達成感を味わえるように工夫する
(2)他の人よりも勉強をして、成長している自分を感じる
以上の2点のようなことを守っていけば、自然と勉強が楽しくなっていくはずです!
もちろん、これは私の場合を書いたのですが、勉強が好きになれずに悩まれている方、ぜひ実践してみてください。
どうすれば、勉強がよりできるようになるかということに関しては、また時期を開けてお伝えできればと思います。