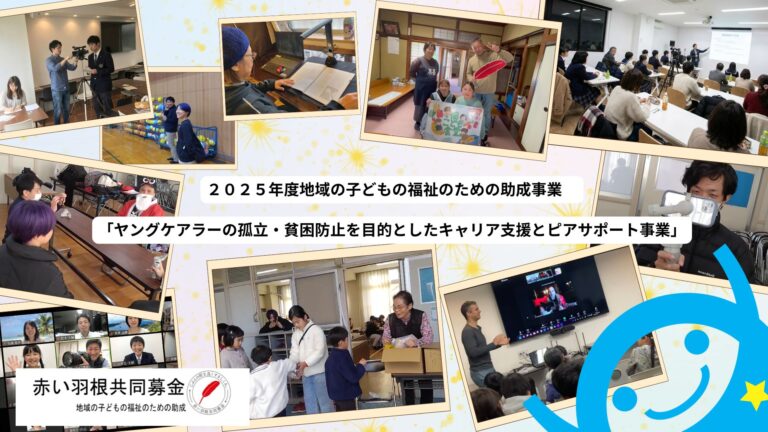今日はわかこくの理事、濱田さんよりアフリカからの投稿です。
日本のガラパゴス化の第二章は始まっている
インターネットが発達して本当に便利になった。
知りたい情報はいくらでもタダで手に入るし、SNSで友人知人とのコミュニケーションも楽々だ。
「世界を旅してきました!」と切り出しておいて、
「ただし、インターネットの世界でね」( ´,_ゝ`)
とオチをつける猛者もいるかもしれない
思い出すのは、ひと昔前、日本の総合家電メーカーが作った携帯電話が、「ガラパゴス化」と皮肉られていた時期があったこと。
携帯電話の規格や仕様が日本に必要十分以上に適応されてしまって、世界の規格や仕様、ニーズなどと異なってしまい、世界を相手にしたビジネスができなくなった、という残念な話だ。
そして最近、このガラパゴス化の第二章が始まっているのではないか、というのが私の持論である。

ガラパゴス化はハード(物)からソフト(人間)へ、とさらに進行しているのではないか。
例えば、日本のSNSの代表格となっているLINEでの毎日のコミュニケーション。
ごくごく限られた親しい日本人の友人とだけ会話して満足してしまう人が、まだまだ多いのではないか。
親しい日本人同士とのつながりで、安心したいところだろうが、海外を拠点に仕事をした人間なら誰しもそんな閉鎖的な人間関係をなつかしくさえ思うだろう。
日本社会の国内問題に囚われて、いつまでも変化できない人の共通点に、この閉鎖的なつながりで凝縮していく傾向があるように思う。
日本国内にしかいない人間が、国内のことを分かった気になってしまう。
抑うつ的なストレスを感じているサラリーマンや子育て世代のなかには、日本社会に見られる同調圧力やピアプレッシャーでわざわざ自分たちを生きづらい心境にしていくことに拍車をかけ合っている人もいるのではないか。

世界の中の日本のはずなのに、日本人だけでつるんで世界が見えなくなっているのではないだろうか。
あなたのLINEやFACEBOOKの友達の中に、外国人やマイノリティなど、自分とは大きく異なる価値観や考え方、または生き方や働き方を実践している友人知人が何人いるか、確認してみて欲しい。
まったくいない、という人は次に自分の悩みに変化がここ数年、あったかとも自問してみて欲しい。
虫歯になっても自宅でじっとしていて痛みは消えない
あるいは、
室内に生ゴミを置いたまま、「いつまでたっても部屋が臭い」と悩んでいるような、徒労の数年を過ごしていないか、考えてみてほしい。
自分に何か変化を起こすためには、今まで自分がしてこなかった行動を起こす必要がある、ということだ。
そして自分自身を変えるとき、きっと自分とは異なる価値観や文化の人々との交流がきっかけになる。
そうすることで、考えかたや価値化の多様性も生まれるだろう。
そんな自分とは価値観が異なる人々と、コミュニケーションをとれているだろうか。
そのようなコミュニケーションが可能となるような、日々の努力や訓練をしてきただろうか。

本当に成長したいならアウェイで戦おう
そんな偉そうなことをとやかく言う筆者は、昨年から、アフリカのマラウイ共和国で緊急援助のプロジェクトに携わっている。
この国はアフリカでも指折りの貧国と聞いていた。
いわゆるGDPと呼ばれる経済指標では最下位争いをしている。
2014年の1人当たり国民所得は250米ドルで、世界最下位である。(Wikipedia マラウイ)
日本にいるスマートフォンからの情報収集に長けた若者たち、「インターネットの旅人たち」は、現実の世界で起きている現象をどのように解釈し、理解していくのだろうか。
どうすれば、理解をするための行動を伴わせていくことができるだろうか。
日本の国内の問題と向き合ってきただけに、ここに来ていつもそんなことを考えてしまうようになった。
インターネットやメディアに転がっている情報というものは、何となく知ったような気分にしてくれる。
「ふーん」と理解したりして、そのまま納得して自分の頭のなかで処理することがよくある。
年間250ドルで生活しているマラウイ人と交流し会話する中で、やはり現場に勝る情報はない、ということを改めて実感している。

会場である小学校(南スーダンビディビディ難民居住区)で撮影
早朝、先生の合図に従って、南スーダンの子供たちが整列している。
資材に乏しく、茅葺きとレンガで作った質素で小さなあばら家に老人(病人)が一人で生活していること。
お金がなく自分で栽培したトウモロコシや豆を毎日ひたすら食べていること
栄養失調に陥っている子供たちがどのような体形をしているのか、飢えるとはどういうことなのか、満足に電気や水が使えない生活とは一体どういうものなのか、などなど。
文字を読むだけで、あったことを知ったことにされてしまう。
しかし、本音を言えば、開発援助や国際支援に関わったことがない方には、インターネットやメディアの情報で知ったかぶりをするのは一切、止めて欲しい。
あるいは、この世界について知らないままこの世界に絶望したり、
貧困について、実際に見て体験していないこと、知らないことを知っているように語ることは辞めてほしい。
海外の現場にある本物の生きた情報に沢山触れて、自分の価値観や考え方、生き方や働き化などを研ぎ澄ませていって欲しい。
私たちが生まれた世界のすべてが、日本だけと思わないで欲しい。

外国人の私に驚く小さな子供
今、海外や途上国に行くチャンスはいくらでもある。
わかこくでも、今年から学生の海外インターンやスタディツアーをラオスで開始する。
時間と少しだけでも貯金があるのなら世界を旅して回るのもよし、JICAの青年海外協力隊になって海外ボランティアをするのも大ありだ。
海外にいく環境や資源は、じゅうぶん整ってきている。
日本を知るために外へ出る
日本という国は、パーフェクトだ。
インターネットはサクサクだし、治安はいいし、人はまじめで優しいし、食べ物も美味い。
毎日、日本人の友達とつるんでペチャクチャ喋るのも、とても楽しい。
日本人にとって自慢の国だろう。
でも、そんな「日本大好き論」を語るのは海外に出てからでも遅くはない。
海外で自分の五感で何かを感じ取る。
海外で学ぶ。
そして日本や日本人との違いを知る。
そうやってアウェイでの生活や活動を四苦八苦する中で、あなたの日本大好き論は、ますます深みと広がりを持った魅力的なものになるだろう。
そして、そういった若い人たちひとり一人のやる気と頑張りが、多様性に富んだ日本をもたらしてくれる。
日本の四季に富んだ多様性ある動植物の自然を美しいと感じるように、価値観や文化の多様性も美しい日本になって欲しい。
ウガンダ北部の南スーダン難民居住区にて 濱田昌大