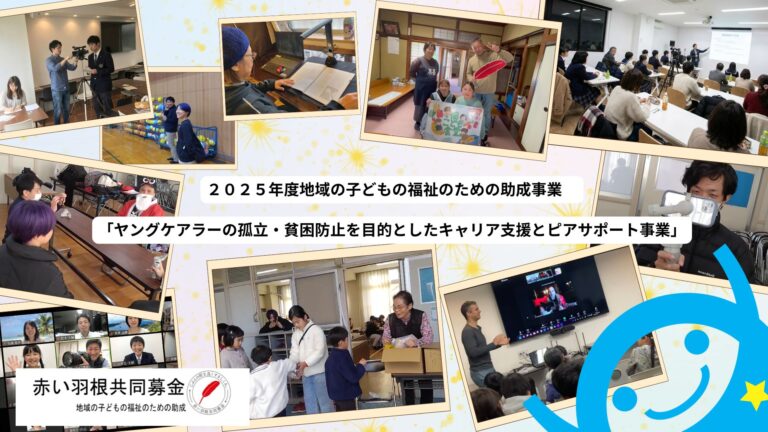NPO法人Wisaは、不登校・ひきこもりの問題解決を2009年より開始しきました。特に2018年より、不登校のなかでも外国にルーツのあるご家庭の家族・進学について支援を開始しました。
「外国にルーツをもつヤングケアラー」(”Young Carers with Foreign Roots”|YCFR)というテーマは、まだ新しい社会問題として多くの人に知られていません。
日本社会における「ヤングケアラー問題」に加え、異文化背景や言語の壁、社会的孤立などが影響する複雑な課題を含んでいます。
ヤングケアラーとは、家族の世話や介護を日常的に担う子供・若者のことで、特に義務教育や社会活動に支障が出る場合があります。外国にルーツを持つヤングケアラーの場合、以下のような特有の課題があります:
1. 言語の壁
外国にルーツを持つ子供たちは、家族内では母語を話し、学校や地域社会では日本語を使うことが多いです。親が日本語を十分に理解できない場合、子供が翻訳や通訳の役割を果たし、行政手続きや医療の場面でも介護の一環として働くことがあります。これは、負担が大きいだけでなく、彼らの成長や教育にも悪影響を及ぼす可能性があります。
2. 文化的・社会的孤立
外国にルーツを持つ家族は、地域社会とのつながりが弱く、孤立しやすい傾向があります。文化や宗教的な違いから、家族内のケアに対する考え方が日本社会の一般的なものと異なる場合もあり、サポートを受けるための情報やリソースにアクセスするのが難しい場合があります。
3. 教育と進学への影響
家庭でのケアが優先されるため、ヤングケアラーは学校生活に十分に参加できず、学業成績や進学の機会に影響を及ぼすことがあります。特に外国にルーツを持つ場合、文化的な違いや支援の少なさが進学の選択肢をさらに狭めることが考えられます。
4. 精神的負担と心理的な影響
ヤングケアラーとしての役割は、ストレスや疲労、孤独感を引き起こすことがあり、長期的な精神的な影響も懸念されます。外国にルーツを持つ場合、同世代との共通の話題が少なくなり、さらに孤独感が強まる可能性があります。
5. サポート体制の不足
日本社会では、外国にルーツを持つヤングケアラーに対するサポート体制が十分に整っているとは言い難いです。地域社会や学校、行政機関は、こうした若者たちに対して支援を行う必要があり、特に多言語対応や文化的理解が求められます。
これらの問題に対処するためには、教育機関や行政が多文化共生の視点からサポート体制を強化し、ヤングケアラーが安心して生活できる環境作りが必要です。また、コミュニティや支援団体が外国にルーツを持つ家族に対して理解を深め、適切なケアが提供されるような仕組みも重要です。
――――――――――――――
NPO法人Wisaでは東南アジア圏でよく使用される、Whatsapp&Facebookに相談窓口を設けて、外国にルーツのあるヤングケアラー(YCFR)の支援を開始しています。
YCFRについて講演のご依頼、ボランティア(にほんご教育支援)参加のご相談はこちらのGoogleフォームからお気軽にご連絡ください。