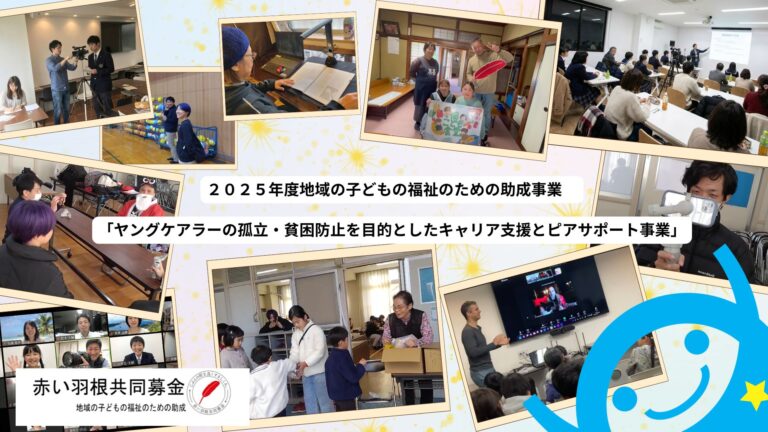はじめに
私たちが日々直面している若者支援の現場は、急速にデジタル化しつつあります。スマートフォンを中心とした日常生活、SNSでの交流、AIやゲームとの関わり。若者の暮らしのなかに、テクノロジーはすでに深く組み込まれています。にもかかわらず、日本のユースワーク(青少年支援)の現場では、「デジタル」と「ユースワーク」がまだ十分に結びついているとは言えません。
そこでWisaはデジタル・ユースワークについての調査研究プロジェクト「Wisaアクション・リサーチセンター and パブリケーション」を2025年度より自主事業としてスタートし、まず初めにフィンランドの先進的な実践をまとめた『デジタル・ユースワーク ― フィンランドの視点(Verke編)』を翻訳・紹介していくことにしました。
フィンランドは、若者の参加と社会的包摂を重視するユースワーク政策において、欧州でも高い評価を得ており、その中でも特に「デジタル技術をどうユースワークに活かすか」という点で、他国に先駆けた取り組みを行ってきました。自治体、教会、NGO、学校、行政、研究機関が一体となり、若者の視点に立った実験的・実践的なユースワークを展開しています。
本書はその成果を理論と実践の両面から紹介した、まさにデジタルユースワークの「教科書」とも言える内容です。
日本でも、不登校、ひきこもり、孤立、情報過多、依存症、ジェンダーや多様性の課題など、若者の生活とテクノロジーが複雑に絡み合う現実があります。フィンランドの経験は、日本の文脈にそのまま当てはめられるわけではありませんが、「どうすればテクノロジーを若者の成長や参加、安心、安全につなげられるのか」を考えるうえで、非常に多くのヒントを与えてくれます。
この翻訳紹介が、日本におけるデジタルユースワークの理論と実践を広げるための一助となり、支援者や教育者、研究者、政策担当者、そして何より若者自身が、より良い未来を共に構想していく手がかりとなることを願っています。
*翻訳紹介する文献は、クリエイティブ・コモンズ:the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenseとして翻訳公開ができるものを対象としています。
デジタルユースワーク定義②(本文p.14-15)
デジタル・ユースワークは、現在、多くの国際的な場で概念として導入されています。国によっては、同様の考え方を「スマート・ユースワーク(Smart Youth Work)」という用語で表現している場合もあります。EUの「デジタル化と青少年に関する専門家グループ(EU Expert Group)」は、2017年にデジタル・ユースワークの定義を以下のようにまとめています。
-
デジタル・ユースワークとは、ユースワークの実践において、デジタルメディアやテクノロジーを積極的に活用したり、それらに取り組んだりすることを意味します。
-
デジタル・ユースワークは、ユースワークにおける一つの手法ではなく、オープン・ユースワーク、青少年情報サービス、個別支援、グループ活動など、さまざまな場面で実施される可能性があります。
-
デジタル・ユースワークには、一般的なユースワークと目標を同じくします。そして、ユースワークにおいてデジタルメディアやテクノロジーの活用は、その目標の達成に貢献するものでなければなりません。
-
デジタル・ユースワークは、対面環境、オンライン環境、あるいはその両方が混在したハイブリッドな環境の中でも行うことができます。デジタルメディアやテクノロジーは、ユースワークのツール、活動、またはコンテンツとして用いられます。
このような定義から読み取れるように、デジタルという性質はそれ自体に価値があるわけではなく、ユースワークの実践においては、あくまでもその目的の達成にどのように貢献するかという観点から活用されるべきであると考えられています。
私たちは、デジタル技術を用いたユースワークとそうでないユースワークとの間に、明確な区別が存在しないような未来、すなわちデジタルメディアが若者の日常生活と同じように、自然にユースワークの一部として存在する未来を目指すべきであると考えます(Lauha et al.)*。
また、デジタル・ユースワークは、時代の変化に応じて常に変化し続けるものです。デジタル・ユースワークは成長し、適応し、さまざまな傾向や考え方を取り入れていきます。そのため、デジタル・ユースワークの実践や定義に関する記述の多くは、あるものはすぐに、またあるものは比較的ゆっくりと陳腐化していきます。こうした現象は、デジタル・ユースワークという分野が、非常にエネルギッシュでダイナミックであることの証でもあります。
*Lauha, H., Tuominen, S., Merikivi, J. and P. Timonen 2017. Minne menet, digitaalinen nuorisotyö? in Hoikkala, T. & J. Kuivakangas (Eds.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät
ja mahdollisuudet. Humak & Nuorisotutkimusverkosto.
デジタル・ユースワークの定義とその重要性(本文 pp.17-18)
エマ・クーシ(教育文化省)
Emma Kuusi, Ministry of Education and Culture
フィンランドでは、2017年初頭に新たな青少年法が施行されました。この法律の目的は、若者の社会的包摂を促進し、社会参加や社会的影響力の拡大し、社会で生きていくために必要な知識とスキルを身につける機会を提供することにあります。また、若者の成長や自立、共同体意識を支援し、余暇活動や市民社会への参加を後押しすること、さらに、無差別・平等の価値を推進し、若者の権利を保障し、その生活環境を改善することも目指しています。
これらの目的の根底には、連帯、多文化主義、国際性、持続可能な開発、健康的なライフスタイル、命と環境の尊重、そして分野横断的な協働といった基本的な価値観が据えられています。
新法のもとでは、青少年活動に対する責任は各自治体にあります。自治体は、若者向けのサービスや設備の提供、市民参加の支援などを通じて、若者が主体的に活動できる前提条件を整える義務を負っています。若者たちは、インフォーマルで自立的な活動を行うために、常に安全な居場所と適切な支援を必要としています。
ユースセンターでの活動は、フィンランドのほぼすべての自治体で提供されている伝統的なユースワークのひとつのかたちです。しかし、すべての若者がそうした施設を利用しているわけではありません。実際には、多くの若者が学校外の時間を、街頭やショッピングセンター、カフェ、公共交通機関、そしてデジタル空間など、さまざまな場所で過ごしています。自治体やNGOに所属するユースワーカーたちは、これまでも伝統的にそうした現場で若者と関わってきました。
デジタル・ユースワークの定義
デジタル・ユースワークも、こうした現場の一つと考えることができます。デジタル性(デジタリティ)は、ユースワークの「環境」だけでなく、その「手段」や「内容」にも深く関係しています。テクノロジーの進展により、デジタル性は常に変化しており、それに伴ってユースワークも変化が求められているのです。
ユースワークの一形態として、デジタル・ユースワークは、ユースワーカーにとってまだ馴染みのない、あるいは不足していると感じるスキルや知識を必要とするものでしょう。現在では、ユースワークの職業訓練課程においてもデジタル・ユースワークが取り上げられるようになってきていますが、現場で実践するにはさらなる研修や支援が継続的に求められています。
教育文化省は、青少年法に基づいてユースワークおよび青少年政策の統括、調整、発展、政府による政策形成の支援などを担っています。これらを遂行するためには、最新の情報と、デジタル・ユースワークに対する正確な理解が不可欠です。
こうした背景から、教育文化省は国の支援機関であるVerkeに資金提供を行っています。Verkeは、デジタル・ユースワークに関する情報を収集・編集するだけでなく、実践者向けの研修や支援サービスも提供しており、一般市民への啓発と実践の質の向上に寄与しています。将来的には、デジタル化がすべてのユースワークにおいて当たり前のものとなり、Verkeのような独立機関が不要になるかもしれません。しかし、現時点ではその段階には未だ至っていないのが現実です。
このほかにも教育文化省は、デジタル・ユースワークの立ち上げや発展を目指す自治体やNGOによるプロジェクトにも助成を行っています。この助成金は、ユースワークの手法や地域的条件の観点から、革新的な取り組みを支援することを目的としています。
この助成によってユースワークにおけるデジタルメディアの活用を促進し、デジタル・ユースワークの内容をさらに発展させていくのです。こうしたプロジェクトには、従来のユースワークが十分に届いていなかった若者が参加することも少なくありません。
デジタル化は、青少年法の理念に沿って若者支援の新たな方法に可能性を与えています。デジタル化によってより多くの若者にアプローチできるようになり、参加や発言へのハードルを下げ、自由時間の活用や交流のための使いやすいチャンネルを提供することができます。これは、ユースワークの手法を今後さらに発展させていくための、重要な課題でもあります。
次回へ続きます
訳注について
本書は、フィンランドのデジタル・ユースワークに関する報告書『Digital Youth Work – A Finnish Perspective』の内容をもとに、日本の読者向けに翻訳・紹介したものです。ただし、本訳は逐語的な完全翻訳ではありません。
原文は主にヨーロッパ、特にフィンランド国内のユースワーク関係者を対象としており、読者層を限定した地理的・制度的背景の記述や実務的な案内が多数含まれているため、日本の文脈では理解が難しい箇所や冗長と判断される情報については、適宜省略・簡略化を行いました。また、日本語としての可読性や論理的な流れを高めるために、段落構成の再編や語順の調整を行っている箇所もあります。
このような編集意図にご理解いただきつつ、日本におけるデジタル・ユースワークの実践と議論の促進に向けた一助としてお読みいただければ幸いです。