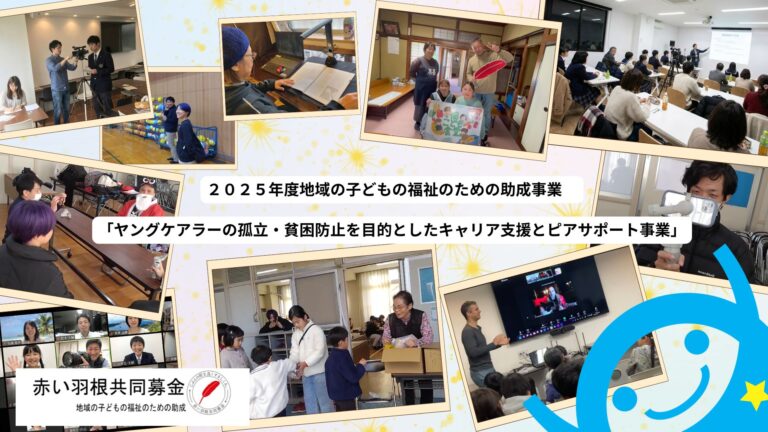はじめに
私たちが日々直面している若者支援の現場は、急速にデジタル化しつつあります。スマートフォンを中心とした日常生活、SNSでの交流、AIやゲームとの関わり。若者の暮らしのなかに、テクノロジーはすでに深く組み込まれています。にもかかわらず、日本のユースワーク(青少年支援)の現場では、「デジタル」と「ユースワーク」がまだ十分に結びついているとは言えません。
そこでWisaはデジタル・ユースワークについての調査研究プロジェクト「Wisaアクション・リサーチセンター and パブリケーション」を2025年度より自主事業としてスタートし、まず初めにフィンランドの先進的な実践をまとめた『デジタル・ユースワーク ― フィンランドの視点(Verke編)』を翻訳・紹介していくことにしました。
フィンランドは、若者の参加と社会的包摂を重視するユースワーク政策において、欧州でも高い評価を得ており、その中でも特に「デジタル技術をどうユースワークに活かすか」という点で、他国に先駆けた取り組みを行ってきました。自治体、教会、NGO、学校、行政、研究機関が一体となり、若者の視点に立った実験的・実践的なユースワークを展開しています。
本書はその成果を理論と実践の両面から紹介した、まさにデジタルユースワークの「教科書」とも言える内容です。
日本でも、不登校、ひきこもり、孤立、情報過多、依存症、ジェンダーや多様性の課題など、若者の生活とテクノロジーが複雑に絡み合う現実があります。フィンランドの経験は、日本の文脈にそのまま当てはめられるわけではありませんが、「どうすればテクノロジーを若者の成長や参加、安心、安全につなげられるのか」を考えるうえで、非常に多くのヒントを与えてくれます。
この翻訳紹介が、日本におけるデジタルユースワークの理論と実践を広げるための一助となり、支援者や教育者、研究者、政策担当者、そして何より若者自身が、より良い未来を共に構想していく手がかりとなることを願っています。
*翻訳紹介する文献は、クリエイティブ・コモンズ:the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenseとして翻訳公開ができるものを対象としています。
序文
高度に発達したデジタルテクノロジーが、若者の生活のあらゆる側面に深く浸透する時代となりました。デジタルメディアを積極的に使うにせよ、受動的に使うにせよ、すべての若者は何らかのかたちでデジタル文化とつながっています。テクノロジーの進展は、若者に求められる市民スキルや人間関係の築き方を根本的に変えつつあるのです。したがって、ユースワーク(若者支援)のデジタル化は、もはや時代に応じた選択肢ではなく、不可避な要件となろうとしています。
フィンランドのユースワークは、オンラインプラットフォームの可能性を非常に早い段階から積極的に試みてきました。しかし、オンライン技術やスマートフォンを導入すること自体が、活動の価値や新しさを保証するわけではありません。とりわけ、若者のメディア利用が常に変化していることを考えれば、ユースワークの現場もそれに応じて継続的に更新される必要があります。ユースワークの目的を達成するために、デジタル技術やツールをいかに活用するかが問われています。
言い換えれば、デジタル・ユースワークとは、デジタルメディアやテクノロジーをユースワークに応用する取り組みです。目指すところは、デジタル技術を道具(手段)として活用し、ユースワークの目的達成や組織の活動そのものを促進・推進することが目的です。私たちVerke*の経験に基づけば、デジタル・ユースワークの目的は大きく2つの軸に分けて考えることができます。
[訳注*]Verke(ヴェルケ):フィンランドにおけるデジタル・ユースワーク専門センター。2011年よりフィンランド教育文化省の資金提供を受けて運営され、ヘルシンキ市が事務局を担う。常勤スタッフ7名がデジタル技術とユースワークの連携に取り組んでおり、研修・教材制作・コンサルティング・ネットワーキング・調査研究を通じて、全国の専門職への支援を行っている。近年は特に、革新的な実践支援とユースワーク研修におけるデジタル・リテラシー向上を重点目標としている。
全国の自治体や教区、非政府組織(NGO)では、すでに多くの優れた実践が積み重ねられてきています。しかしVerkeの調査によれば、フィンランド全体でデジタル・ユースワークの取り組みは、まだ始まったばかりだとも言える状況です。デジタル・メディアやテクノロジーの潜在力は、ユースワークの現場でまだ十分には活かされていないのです。デジタル・ユースワークに関する戦略的な取り組みや明確な目標設定も、いまだ限られた事例にとどまっています。
この出版物が、ユースワークのデジタル化とは何を意味するのか、またなぜその実践が重要なのかを理解する手助けとなれば幸いです。本書では、デジタル・ユースワークへのさまざまなアプローチに光を当てる視点を集め、実践的な取り組みと概念的な議論の両面からバランスよく構成するように留意しました。これは、フィンランドのユースワークに根付く「実践から学ぶ」姿勢を大切にしながら、より広い背景や戦略を踏まえて新しい取り組みを模索する姿勢を反映したものです。
掲載されている記事のいくつかは、フィンランド語で既にVerkeのブログや資料に掲載されたものもありますが、多くはこの出版のために新たに書き下ろしました。
フィンランド語圏は小さく、これまでのデジタル・ユースワークに関する情報は主にフィンランド語で発信されてきたため、海外の読者にとってフィンランドで何が、なぜ行われているのかを理解するのは容易ではありませんでした。本書の目的は、フィンランドにおけるデジタル・ユースワークの現状を、より広い読者層に届けることです。
デジタル・ユースワークは、それぞれの国の事情に応じて異なる形で発展してきました。だからこそ、各国の実践者たちが互いに学び合えることは多いはずです。本書が、国際的な協力のなかでデジタル・ユースワークを発展させる起点となり、フィンランド内外の専門家や組織との対話を促進し、活性化させる一助となれば幸いです。
この出版に協力いただいた執筆者の皆さま、そして文部科学省に、心より感謝申し上げます。
2017年9月、ヘルシンキにて
ユハ・キビニエミ & スヴィ・トゥオミネン
デジタル・ユースワークの定義①
テクノロジーの進歩によって、若者たちのインターネット利用のあり方は大きく変化しています。それに伴い、デジタル技術を活用したユースワークも、転換期を迎えています。そのため、デジタル・ユースワークを対面型のユースワークと区別したり、ユースワークとは別個の手法や分野として扱うことはもはや適切とは言えません。むしろ、デジタル・ユースワークはオンライン上で行われる活動に限定されるべきではなく、ユースワークのあらゆる形態と方法に浸透していくものなのです。そもそも、従来型のユースワークと切り離しては、デジタル・ユースワークは成り立ちません。
「デジタル・ユースワーク」という言葉がフィンランドのユースワークの語彙に初めて登場したのは、2012年の夏のことでした。Verke(ヴェルケ)の招待によって、ヨーロッパ各地のユースワーク団体がフィンランドに集まり、デジタル化がユースワークやその実践にもたらす影響について議論しました。その時すでに、テクノロジーやデジタル化が進む社会の中で、若者の主体性を包括的に高めることが、デジタル・ユースワークの目的であるべきだという考えが共有されていました(Davies 2012*、Taylor 2012**)。
とはいえ、「デジタル・ユースワーク」という概念が本格的に定着したのは、それから数年後のことです。当時すでに、オンラインやウェブを活用したユースワークは専門用語の一部として根付いていましたが、実際のユースワークの現場では、特定のアプローチのみが確立されていたにすぎませんでした。多くの国と比較しても、フィンランドのデジタル・ユースワークは、オンラインサービス、特にソーシャルメディアを使った活動に特徴づけられています。同時に、若者とつながるためのチャットツールの活用も進んでいます。
実際、多くのユースワーカーにとって、「ソーシャルメディア以外のデジタル・メディアとは何か」を理解するのが難しいのが現状です。そのため、オンラインやウェブベースのユースワークという表現だけでは表現しきれない多様な実践をカバーしていくために、「デジタル・ユースワーク」という包括的な概念が求められていたのです(Lauha et al. 2017***)。
* Davies, T. 2012. The Digital Edge – Nominet Trust announce new funding challenge. <http://www.timdavies.org.uk/2012/06/11/the-digital-edge-nominet-trust-announce-new-fundingchallenge/>, (visited on 19/07/2017).
**Taylor, T. 2012. Digital Youth Work: Towards a Definition and Practice. https://indefenceofyouthwork.com/2012/06/13/digital-youth-work-towards-a-definition-and-practice/, (visited on 19/07/2017).
***Lauha, H., Tuominen, S., Merikivi, J. and P. Timonen 2017. Minne menet, digitaalinen nuorisotyö? in Hoikkala, T. & J. Kuivakangas (Eds.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät
ja mahdollisuudet. Humak & Nuorisotutkimusverkosto.
次回へ続きます
訳注について
本書は、フィンランドのデジタル・ユースワークに関する報告書『Digital Youth Work – A Finnish Perspective』の内容をもとに、日本の読者向けに翻訳・紹介したものです。ただし、本訳は逐語的な完全翻訳ではありません。
原文は主にヨーロッパ、特にフィンランド国内のユースワーク関係者を対象としており、読者層を限定した地理的・制度的背景の記述や実務的な案内が多数含まれているため、日本の文脈では理解が難しい箇所や冗長と判断される情報については、適宜省略・簡略化を行いました。また、日本語としての可読性や論理的な流れを高めるために、段落構成の再編や語順の調整を行っている箇所もあります。
このような編集意図にご理解いただきつつ、日本におけるデジタル・ユースワークの実践と議論の促進に向けた一助としてお読みいただければ幸いです。