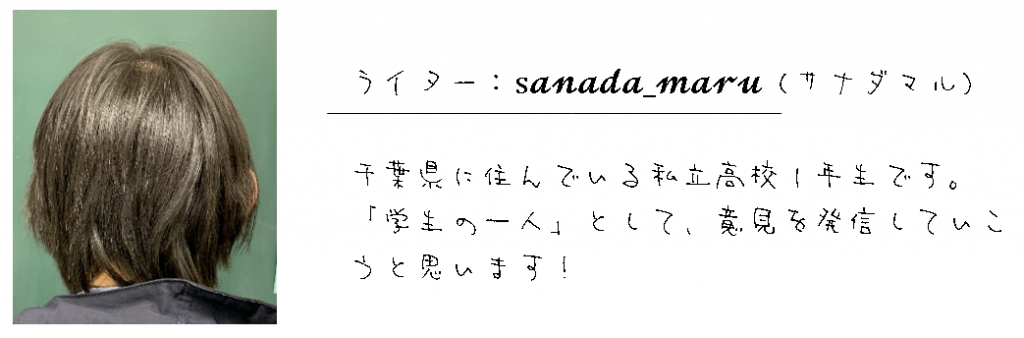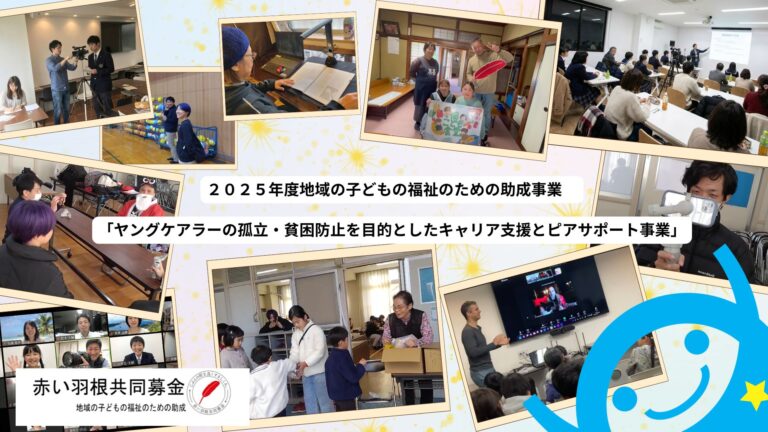はじめに
こんにちは。ライターのsanada_maruです。先日、わかこくのサイトがリニューアルされ、以前にもまして見やすくなり、それに伴い、記事の作成の幅が広がったとのことですので、新機能を使いながら(使えているのかな?)、記事を作成していきたいと思います。
今回の狙い
今回の狙いは、ずばり「説得力のある文章」について。つまり、どれほど多くの人を納得させることができるかについて、伝えていくことにあります。
それに伴い、今回は少しいつもと記事のつくり方を変えて(いつもは下書きを自分のワードファイルで作成して、ある程度校正を加えたうえで投稿しています)書いていきたいと思います。
説得力とは何か
「説得力」という単語を分解すると、「説得」と「力」となります。相手を「説得」つまり、説明したうえで、自分たちの主張を正しいもの、あるいは理解のできるものにしなければなりません。
また「力」というものは相手に「強いる」といった意味合いもあり、半ば無理やりにでもこちらの意見について理解してもらうということに当たります。
さて、この「説得力」ですが、これを上げるためには、まず人間の心理をつかまなければなりません。私たちは、1人の人間として生活していますが、もちろん納得させる相手も人間ですから、互いに考えていることには違いが発生します。
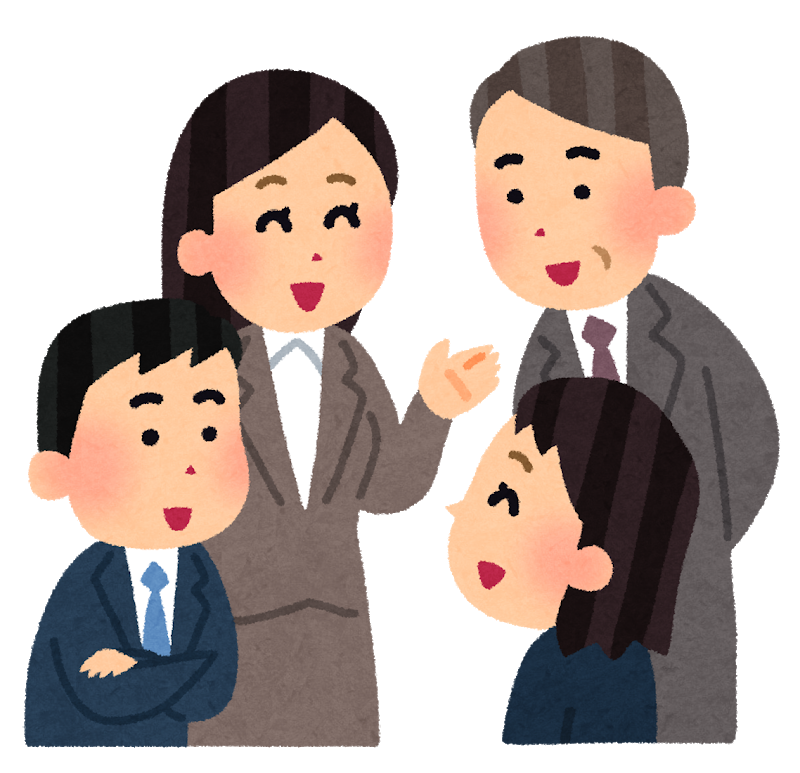
つまり、相手に分かるように伝えなければなりません。ここで、まずは自分が日ごろ相手を説得させようとしている時に、何をしているかを考えてみてください(私も振り返ってみます)。
もしここで、「俺の言ってることは正しいのだ!」だとか「相手が全てを理解してくれている」などと思っている方がいらっしゃれば、その方も、いや、その方こそ、もう一度振り返ってみるといいかもしれません(本当に説得力がある方はここになど来ないでしょう)。
いかがでしょうか。とはいっても、振り返っても、何が間違っているのだ、とかどうすればいいのかとか、何も説明しない状態では振り返っても意味がないですよね。では、私なりの説得力の上げ方を伝えていきたいと思います。
ポイント①:語尾に気をつけよ
人間、見た目が8割といわれることがあります。これは、科学的にみてみるとよくわかります。人間は耳が前方にしかついておらず、後ろの音に疎い傾向にあります。また、目は最大で240度ほどの視野しか確保することができず、やはりこれも後方には弱いのです。触覚に関しては、人間は服を着てしまっているために全体的にこれに制限を受け、他の動物に比べると強くはないのです。
つまり、ここで何が言いたいかというと「人間は目で見たもので大まかな判断をする」ということです。ではなぜこういう話になったかといえば、それはこういったブログの記事の例があるからです。
人間と会話をするうえでは、確かに相手の顔を見て話すことができます。人間の目の動きから口の動き、手の動きや髪の毛の動きまでそれはもう事細かに確認することができるでしょう。
しかし、ブログ記事を含めたネット環境にある時はどうでしょうか。わかこくでも記事の下には、ブロガーの個人情報が一部書かれていますが、それでも顔は見ることができませんし、それもリアルタイムではありません。
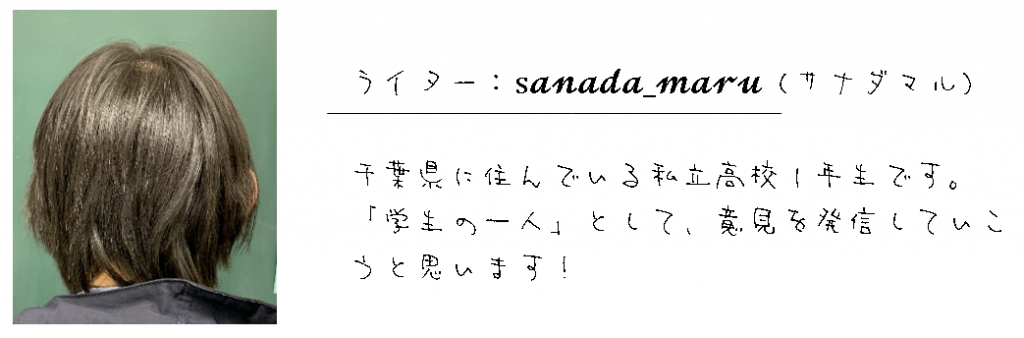
そのような状態で、相手に話を納得させる、心を開いてもらうためには、やはり話し方が重要なのです。
話し方は主に3つあります。
①です・ます調(文語・敬体)
②である・だ調(文語・常体)
③でしょ・ね調(口語)
このうち説得力があるというのはどれでしょうか。そう、それは①と②です。もし、③を選んでしまった方がいるとすれば、やはりこの記事を読み続けるか、あるいは小説などを読み込んだ方がよろしいでしょう。会話、記事であるとはいえ、③に説得力が出てきてしまえば、それはもはや末期でしょう。
なぜ①と②がいいのか。それには理由があります。それは「一貫している」という点にあります。説得力を持たせる場合、一般的に(後で詳しく書きますが)エビデンス(証拠・根拠)が重要になってきます。

つまり、それらが多ければ多いほど、当然文章は長くなっていくのです。そのような中で、説得力を持たせるためには、首尾一貫してその主張を続けなければならないのです。
皆さんも、何かを批判する人がいたとして、その人が途中で主張を変えてしまったら、その人に対しての信用はできないと思ってしまうはずです。
それに似たようなもので、途中で語尾を変えてしまうということは、自分の中での主張が組み立てられていないということを表しているのです。
ですから、同じ文章の中では(本であればその一冊。記事であればその一本)常に同じ形態をとらなければならないのです。これは説得力もありますが、その云々の前に、日本語として理解しなければならないポイントでもあります(ただし、括弧の中はそうでなくても構わない場合が多い)。
では、①と②はどのような使い分けをすればいいのか。それは、主張の強さと、相手に対する丁寧さによって変えるとふさわしいと、一般的に思われています。
例えば①と②を見ると、①ではなんだか物腰が柔らかそうなイメージを、②には決めつけといったイメージを抱くと思います。

時として、そういったイメージは当たるもので、多くの場合、丁寧な主張であれば①が使われることの方が多いです。これは敬体という言葉が表しているように、相手に対して「敬意」を払っているということを表しているのです。
前回の私の記事でも書いた通り、多くの主張はディベートと同じように、中立性や丁寧性を求められます。相手に対して主張をするのですから、それは当然のことともいえます。納得してほしいのであれば、私たちもそれなりの敬意を払えということなのです。
対して、それが常に正しいこと、つまり不変の真理である場合は②が多く使われます。論文など中立性が求められ、かつ断定的に正しいことを主張する場合にはこれが多く用いられます。
私も、こういった法則を遵守するように心掛けています。尤も、いつもこれができているかと尋ねられると、いささか一抹の不安がよぎりますが、それでも過去の記事を読み返していただけると、その主張の強さに応じて文体が変わっているのではないかと思っています。
まだまだこの話は続きがありますが、説得力は話が長ければ長いほどいい、というわけでもありません。読者の方も、お疲れかと思います。今回はここでいったん終了し、また次回の記事でお目にかかりたいと思います。
ご精読ありがとうございました。